私が考える歩き方とスキーの滑りの関係についてです。
もともとは右足の脛骨と腓骨の骨折後のリハビリ時に調べ、今でも実践している(習慣になった)ことです。
この歩き方を練習することで、膝が内側に入る、過度にインエッジに荷重するなど、内倒の原因となる動作が出にくくなります。
足裏の荷重点
まず始めに、歩行時に重心が足の裏のどの部分にあるか思い起こしてください。
状況が許すならば、実際に歩いて荷重点の移動を確認してください。
普通に平地を歩く時、足は踵から着地をし母指球で蹴りだすように地面から離れます。
すなわち、重心は踵から母指球に移動します。
歩くとは、左右の足が交互に、この動作を繰り返すことです。
しかし、重心移動の仕方には個性があります。
重心移動のパターン
足の向きと重心移動を3パターンに分けてみました。
図1
- 足の向き:足の内側が進行方向(進行方向よりも外側の場合も含む)
- 重心移動:直線的
図2
- 足の向き:足の内側が進行方向
- 重心移動:曲線的(小指球を経由して母指球に)
図3
- 足の向き:足の外側が進行方向
- 重心移動:曲線的(小指球を経由して母指球に)
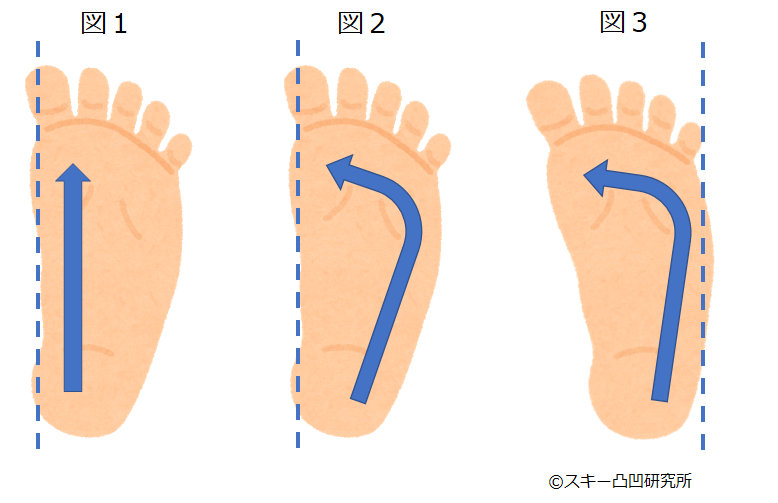
みなさんの歩き方はどのパターンですか。
今まで歩き方をあまり意識したことのない方は、図1の重心移動を行っている方が多いのではないでしょうか。
滑り方との関係
スキーをしている時のブーツの中はどうなっているか考えてみましょう。
まず、足の向きですがブーツは板に取り付けられていて、図1と図3の中間ぐらいです。
次に重心移動ですが、歩行と違って板とブーツは固定されているので、地面を踏み切る動作はなく、重心は直線的に、踵から5本の指のどこかの方向に移動します。
また、重心の移動も歩行時に比べれば少なくなります。
ここで外足に注目してみたいと思います。
切替で図1のように足の内側を踵から母指球方向に重心が移動する場合、上体が内側に入り内倒しやすくなります。
また、谷回りでエッジが立ちやすく、板を体から離しづらくなります。
次に切替で図3のように足の外側、踵から小指球方向に重心が移動した場合はどうでしょうか。
しっかりと外足に荷重ができ、また谷回りで板を体から離しやすくなります。
O脚
O脚の方はさらに注意が必要です。
O脚の方が踵を付けて立つと、内側が少し軽くなり外側に重心がよります。
足を少し開き、足の裏が床にぴったりと着くように立った場合、屈むと膝は内側に入ってきます。
スキーブーツのインソールなどの調整を行っていない場合、滑っている時も同じことが起こり、膝を曲げると内側に重心が入りすぎることになります。
最後に
みなさんの歩き方はどのパターンでしたか。
今の滑りに悩んでいるようであれば、オフシーズンの間に歩き方から変えてみるのも一つの方法かもしれません。
特に内倒する方にとっては、図3のパターンの歩き方の練習は効果的です。
少なくとも私は、歩き方を変えて滑りが激変しました。

コメント