国土交通省観光庁より、「スノーリゾートの投資環境整備に関する検討会」の報告書が2020年4月28日に公表されました。
大変すばらしい内容で、みごとに日本のスキー場の現状を把握、分析したのち、発展のための提言を行っています。
全ての雪山を愛する人にぜひ読んでいただきたいと思うのですが、私なりのまとめと感想を述べようと思います。
#報告書は全23頁で、補足資料も多くあります。ここで紹介する内容はほんのごく一部なので、興味を持たれた方はブログの最後にリンクを張っておきますのでご覧ください。
理想のスキー場
報告書のなかで、望まれるスキー場像が描かれています。
それらの中から何点かポイントを抜き出してみました。
スキー場の規模
魅力あるスキー場として、その規模は重要です。
具体的な数は上げていませんが、索道(リフト+ゴンドラ)が5本以上と未満で黒字化率に大きな差があるというデータが出ていました。
スキー場とその付帯事業の一体運営
衝撃だったのは、索道事業(リフト、ゴンドラ)は儲からないということでした。
利益が高いのは、スキー場に付帯するレストラン、レンタル、スクールなどの付帯事業だということです。
しかし、スキー場の魅力としては索道が最も重要な要素の一つです。
索道に投資することができる事業構造が求められています。
ベースタウンの活性化
スキー場に人を集めるためには、ベースタウンのベッド数が重要とのことでした。
ライト層にとって、スキー場を含めた温泉、買い物、街での食事なども楽しみにしています。
現実のスキー場
みなさんがホームとしているスキー場を思い出してください。
理想のスキー場に近いところもあるかと思いますが、多くのスキー場は次のような事業形態ではないでしょうか。
- 小規模なスキー場
- 中・大規模なスキー場だが、
- 複数の索道(リフト)会社が運営
- ゲレンデ内に点在する地元の食堂、レンタル企業、スキースクール
結果として、索道会社は利益を上げることができないので設備投資を行うことができずリフトの老朽化が進み、ますます利用者が少なくなる。
という状態のスキー場が多いですよね。
解決策
ひとことでいうと、個々の経営から一体経営への移行が重要ということが提言されています。
具体的は、スキー場(索道、レストラン、レンタルなど)の一体経営、およびベースタウンの共同所有+個別経営 によるエリア全体がまとまりです。
加えて、融資など具体的な方法まで書かれていました。
暗に示唆しているところ
一方で、明記はされていませんが、次のことが示唆せれているように感じました。
全てのスキー場を救えるわけではない。
特に、小規模なスキー場を救うことは難しい。
おいしいとこどりの既得権益が残ったままだと発展が難しい。
最後に
スキー場は供給過剰な状態が続いていて体力勝負になっています。
報告書にもある通り、中・大規模なスキー場はステークスホルダーが多く、調整に時間がかかります。
また、小規模なスキー場は、地方自治体からの税金で運営されているところも多く、健全な市場原理が働かない状態が続いています。
どちらも、そこで生活をしている方々にとっては、全体最適よりもご自身の生活が大事だと言うことは分かります。
しかし、バブル崩壊後30年が経ち、そろそろ次のステージに進んでいく時だと思います。
ここ10年、スキー・スノーボード人口は安定しており、加えて海外からのインバウンドも見込めます。
スキー場産業自体の発展の可能性は十分にあるので、今の時期にしっかりと基礎をつくっていってほしいです。
スノーリゾート地域の活性化に向けて はこちら

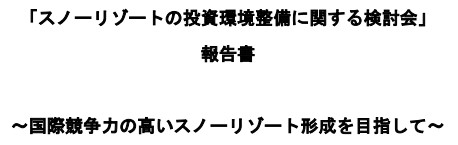
コメント